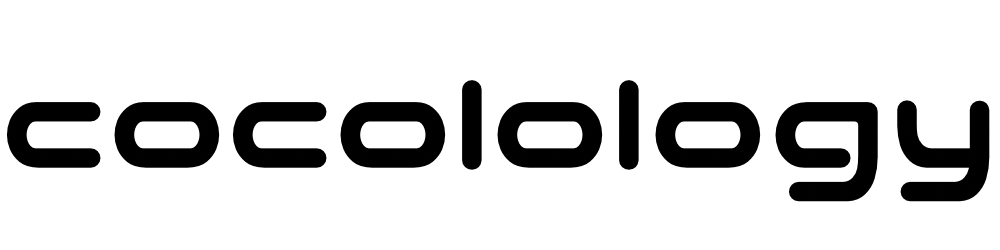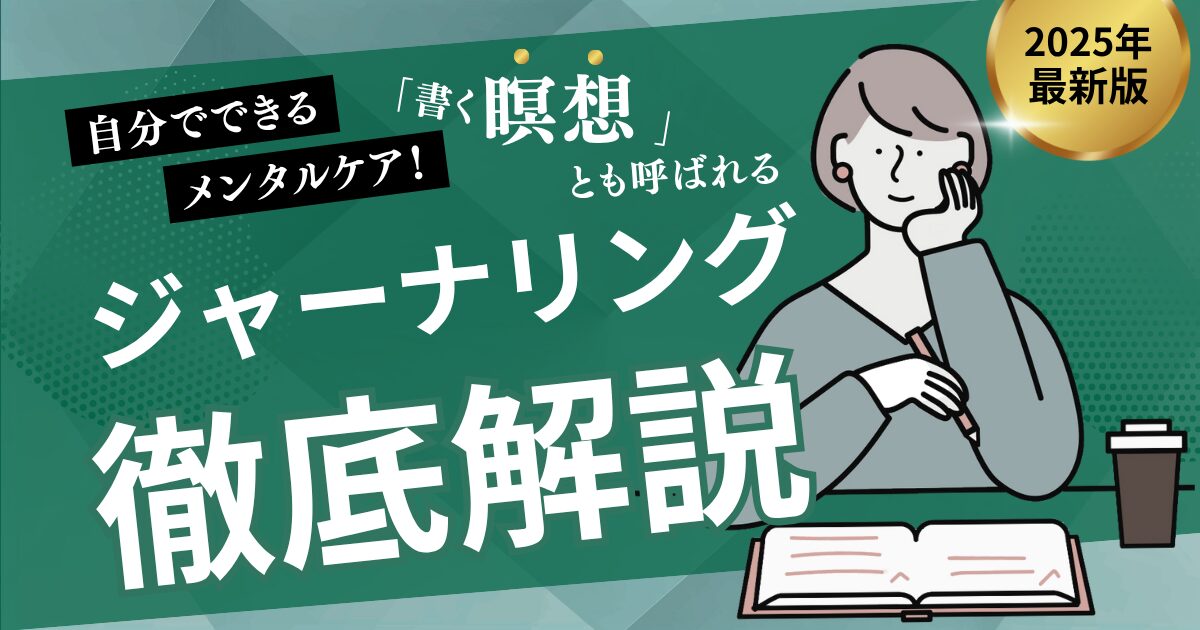内観とは?心の健康を保つ内観のやり方・意味・効果を徹底解説
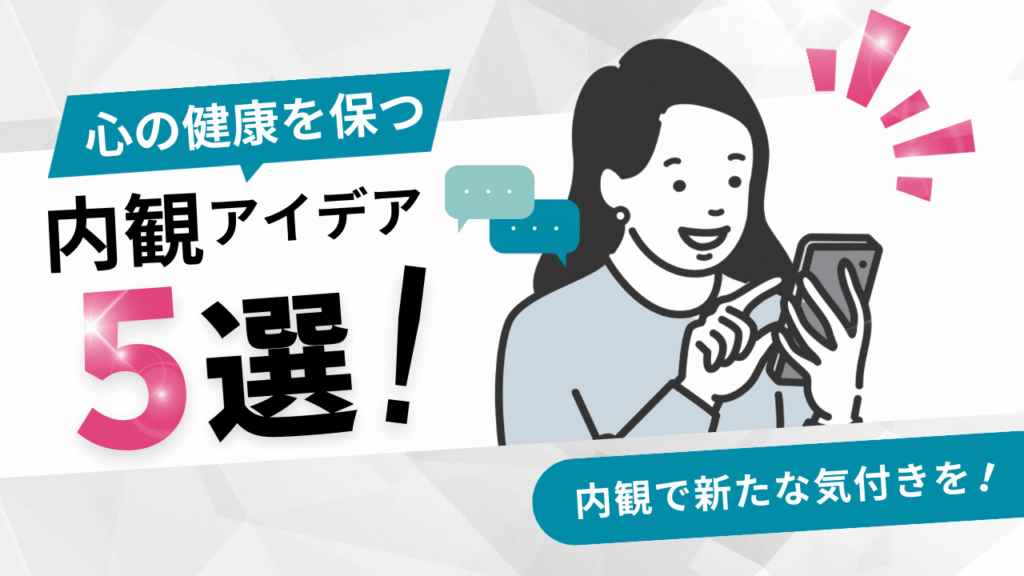
「理由は分からないけど、気分が落ち込む」「自分のことなのに、自分の気持ちがよく分からない」──そんなふうに感じたことはありませんか?これは、自分の心と向き合えていないときに起こりやすいお悩みの一つ。
とはいえ、どうやって自分の心と向き合えばよいのか分からないという方もいるでしょう。そこでおすすめしたいのが、『内観』です。
この記事では、内観の基本から実践方法、さらにスマホで簡単に取り組めるアプリまで、内観に関する情報を幅広くご紹介します。自分らしく、心地良く、感情に振り回されない毎日を送りたいと考えている方にぴったりの内容です。ぜひ最後までご覧ください。
内観とは
内観とは、自分自身の思考や感情の動きを観察する行為のこと。
今でこそ心理学的なイメージの強い内観ですが、もとは仏教で行われていた修行法でした。そんな内観が心理学的な側面を持つようになったのは、1950年代。浄土真宗の修行を体験した吉本伊信氏が心理療法として発展させたことがきっかけです。
この療法は「内観療法」と名付けられ、1960年代には多くの臨床現場で活用されるようになりました。現代においても、内観療法は日本で生まれた心理療法の中でも特に代表的なものとして知られています。
ただし、内観療法は静かな部屋に一定期間こもって行う必要があるなど、専門的な知識や技術を持たない一般人が行うのは難しい側面も。そこで、最近では内観療法のエッセンスを取り入れたシンプルなセルフケア法が発展を見せています。
内観のメリット・効果
内観には、果たしてどのようなメリットがあるのでしょうか?
吉本氏の開発した内観療法はもちろん、内観療法のエッセンスを取り入れたシンプルな内観法にも、数多くのメリットがあります。特によく挙げられるのは、以下の4点でしょう。
- 自己理解を深めるきっかけになる
- 気持ちの整理がしやすくなる
- ネガティブな感情と距離を置きやすくなる
- 過去の経験を客観的に振り返りやすくなる
あなたは、「自分のことは自分が一番分かっている」と思っていませんか?実は心理学では、「人は自分自身のことほど、意外と理解していない」とも考えられています。それでも自分のことを深く理解したいなら、専門の心理学的手法を取るのが一般的。
内観法も、心理療法や自己観察の方法として発展してきた背景があり、自己理解を深める一助になる可能性があります。
例えば、人間関係が上手くいかないとき、内観を通して「本当はどう感じていたのか」「自分は何を求めていたのか」などを深く掘り下げてみると、自分の思考の癖や感情の傾向に気づけるかもしれませんよ。
気持ちの整理がしやすくなる
私たちは、日々さまざまな感情を経験しています。ときには、自分でも理由がよく分からないまま、気持ちが揺れ動いたり、混乱してしまったりすることもあるでしょう。
そんなときには、内観を通して「今、自分は何を感じているのか?」「なぜそう感じたのか?」と振り返ってみるのも一つの方法です。そうすることで、感情の背景に気づいたり、気持ちを整理するきっかけが得られるかもしれません。
ネガティブな感情と距離を置きやすくなる
生きていれば、誰だってネガティブな感情を経験するもの。ですが、そんなときこそ「今、自分はどう感じているのか?」と自分に問いかけ、感情を掘り下げてみましょう。
内観を通して感情を見つめ直す習慣を持つと、例えネガティブな感情であっても、巻き込まれることなく少し距離を置いて眺められるようになるかもしれません。
内観を習慣にすることで、「最近、感情と距離を置けるようになった気がする」と感じられる瞬間が増えていくかもしれませんよ。
過去の経験を客観的に振り返りやすくなる
過去の辛い体験や恥ずかしい失敗など、できれば忘れてしまいたい記憶をふと思い出しては、嫌な気持ちになったことはありませんか?内観は、そうした記憶を事実や背景と冷静に見つめ直すための手法としても活用されています。
感情を整理しながら「なぜあのときそう感じたのか」「本当はどうしたかったのか」と考えることで、当時とは異なる見方に気が付くこともあるでしょう。
また、そうした過去の記憶から、前向きなヒントを得るきっかけになる場合もあります。
内観のデメリット・注意点
それでは、内観にはデメリットや注意点はあるのでしょうか?
実は、内観には多くのメリットが認められている一方で、取り組み方によってはネガティブな影響を受ける可能性もあります。安心して実践するためには、以下の点に注意して取り組むことが大切です。
- ネガティブ思考を助長する危険性がある
- 過去のつらい記憶にとらわれる可能性がある
ネガティブ思考を助長する危険性がある
間違ったやり方で内観に取り組むと、かえってネガティブな考えにとらわれてしまう危険性があります。その結果として、「最近不安を感じることが多い」「よりネガティブな性格になった」と感じる方もいるようです。
ネガティブな思考にとらわれないようにするためにも、『正しい方法で無理なく取り組む』ことを意識して行うようにしましょう。
過去のつらい記憶にとらわれる可能性がある
心療内科や精神科などで治療を受けている方や、過去に強いトラウマを抱えている方の場合、内観の進め方によっては、当時のつらい感情がよみがえってしまうことがあると言われています。
こうしたリスクを避けるためにも、医師やカウンセラーに「内観を行なってよいか」「自分に合った方法はあるか」など、事前に詳しく相談することをおすすめします。
このように、内観にはメリットだけでなく、注意すべき点もあります。
心に負担をかけないようにするためにも、自分に合った方法を選び、無理のないペースで取り組むようにしてくださいね。
無理せず心と向き合いたい方におすすめなのが、スマートフォンアプリ「Awarefy(アウェアファイ)」です。早稲田大学・熊野宏昭研究室との共同研究で、内観に取り組みやすくなるよう設計されています。
アウェアファイには、内観の実践をサポートする機能が盛りだくさん。「コラム法+AIコメント」や「AIタブ」、「コンディションの記録」といった機能を使えば、日々の感情や思考を記録することが可能です。記録を振り返れば、心の状態を見つめ直すきっかけにもなりますよ。
お申し込みはこちら→ストレスに負けないスキルが身につく【Awarefy】
心の健康を保つ内観アイデア5選
せっかく心を整えようと思って内観を始めたのに、かえって辛い気持ちになってしまっては本末転倒ですよね。
そんなトラブルを避けるためにも、自分に合った方法を選んだり、一般に広く推奨されている手順に沿って取り組んだりすることが大切です。ここからは、内観が初めての方でも無理なく取り入れやすい方法を5つご紹介します。
心の健康を保つ内観アイデア①ジャーナリング
ジャーナリングとは、制限時間を決めて、頭に浮かんだことを自由に書き出すセルフケアの手法です。別名「書く瞑想」とも呼ばれ、世界中で多くの人に実践されています。
思考や感情の整理に役立つことから、考えをまとめたいときや、心を落ち着かせたいときによく活用される方法です。また、書いた内容を後から読み返すことで、自分の状況を見つめ直すきっかけにもなります。
ジャーナリングについては、これまでに多くの研究が行われています。特に有名なのが、テキサス大学の心理学者ジェームズ・W・ペネベイカー(James W. Pennebaker)教授の研究です。この研究では、4日連続でジャーナリングを行ったグループと、そうでないグループの心理的な状態やストレスレベルを比較しました。その結果、ジャーナリングを行ったグループのほうが、ストレスレベルや心理的な状態にポジティブな変化が見られたと報告されています。
ジャーナリングのやり方
ジャーナリングは、内観の知識がない方でも取り組みやすい方法の一つ。
ですが、自己流で進めてしまうと、やり方が分からなくなったり、かえって混乱してしまったりすることもあります。効果的にジャーナリングを取り入れるためにも、一般に広く知られている以下の手順を参考にしてみてください。
- 紙とペン、または文章を記録できるスマホアプリを用意する
- テーマと時間を決める(5〜20分など、無理のない範囲がおすすめ)
- タイマーを設定し、時間になったら通知が鳴るようにする
ジャーナリングを実践する上で大切なのは、後から読み返せる状態にしておくこと。例えば、チラシの裏や使い捨てのメモ用紙ではなく、ノートや日記帳を使うとよいでしょう。読み返しやすい媒体に記録しておくことで、振り返りがスムーズになります。
手書きが面倒に感じる方には、先ほどもご紹介したスマートフォンアプリ「Awarefy(アウェアファイ)」が便利。アウェアファイに搭載されている「つぶやき」機能を使えば、思いついたことをサッと記録できます。短時間で記録できることから、自然と習慣化しやすいのが魅力です。
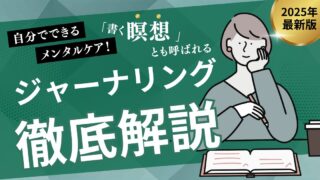
心の健康を保つ内観アイデア②ブレインダンプ
ブレインダンプは、テーマや制限時間を決めずに、頭に浮かんだことをひたすら書き出し、思考を整理する手法です。「思考を捨てる」という名前の通り、書いた内容は読み返さずに破棄することを前提としています。
そのため、丁寧な文章や整った字で書く必要はなく、チラシの裏や使い捨てのメモ用紙を使用しても問題ありません。
教育心理学者のプージャ・K・アガルワル(Pooja K. Agarwal)博士の研究では、授業中にブレインダンプを行うことで生徒の記憶力や理解力が向上したとする結果を報告しています。
こうした知見から、ブレインダンプは思考の整理だけでなく、脳の活性化にもつながる可能性を秘めた手法としても注目されています。
ブレインダンプのやり方
ブレインダンプは、内観的なセルフケアの中でも取り組みやすい方法の一つ。
思いついたことを書き出していくうちに、「頭の中が整理された気がする」「気持ちが落ち着いた」と感じるかもしれません。こうした感覚を得るためにも、以下の一般的に広く知られている手順に沿って行ってみてください。
- 紙とペンを用意する(メモ用紙やコピー用紙、チラシの裏でOK)
- 思いついた思考や感情を、深く考えずに書き起こす
- 書き終わったら潔く捨てる(不要な感情や思考を手放す気持ちで捨てると◎)
ブレインダンプは、内観に関心がある方はもちろん、勉強や仕事を頑張りたいと考えている方にも人気のある手法です。
例えば、勉強中に暗記したい単語を書き出して覚えようとしたり、仕事中に浮かんだ雑念を紙に書いて忘れようとしたりと、シーンに応じて柔軟に取り入れることができます。目的や状況に合わせて自由に使えるのも、ブレインダンプの魅力の一つと言えるでしょう。
心の健康を保つ内観アイデア③認知再構成法
認知再構成法とは、認知行動療法に基づいたセルフケアの手法です。「認知」とは、ものの見方や考え方を指す心理学用語。そして「認知行動療法」は、そうした認知の癖や偏りを修正し、心の健康を保つことを目的とした心理療法です。
認知再構成法では、特定の出来事や感情を書き出し、時間を置いてから見直すことで、偏った思考に気づきやすくなると言われています。その結果、状況を客観視できたり、ネガティブな感情に振り回されにくくなったりする可能性もあります。
フランクリン&マーシャル大学のアリソン・S・トロイ(Allison S. Troy)博士らの研究では、認知再再構成能力(偏ったものの見方や考え方の癖を特定し、よりよい捉え方や考え方に置き換える力)が高い人ほど、自分ではコントロールできないストレスに対して、ネガティブな感情に振り回されにくい傾向があると報告されています。
普段から「つい物事をネガティブに捉えてしまう」「ストレスに振り回されないようにしたい」と感じている方は、認知再構成法を日々のセルフケアに取り入れるのも一つの手かもしれませんね。
認知再構成法のやり方
認知再構成法は、ジャーナリングやブレインダンプと比べると、少し難しい印象を受けるかもしれません。
また、さまざまな手順が存在するため、「どれを試せばよいのか分からない」と感じる方もいるでしょう。ここでは、初めての方でも取り組みやすいやり方を紹介します。
- 紙とペン、または文章を記録できるスマホアプリを用意する
- 特定の状況や、そのときの感情を思い出す
- 頭に思い浮かんだ思考や感情を、そのまま書き出す
- 数分〜数日ほど時間を置いてから、書いた内容を読み返す
- 当時の思考や感情に対して、別の視点から見直してみる
- 新たに気づいたことや、異なる考え方があれば書き加える
この手順を参考にすれば、初めての方でも無理なく取り組めるはず。とはいえ、手順が多くて面倒だと感じる方もいるでしょう。
そんなときには、スマートフォンアプリ「Awarefy(アウェアファイ)」を活用するのも手です。アウェアファイに搭載されている「コラム法+AIコメント」機能には、認知再構成法の手順に沿ったガイドが表示されます。
さらに、記録後にはAIキャラクターからコメントが届くので、偏った考え方に気がつけたり、新しい視点を思いついたりするきっかけとなる可能性があります。
心の健康を保つ内観アイデア④アートコラージュ
アートコラージュは、紙に写真や雑誌の切り抜きなどを自由に貼り付けて、心の状態を表現する方法です。「コラージュで心の整理ができるの?」「ただの遊びじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。
ですが、アートコラージュは1970年代にアメリカの臨床現場で取り入れられて以来、心理療法の手法として長く用いられてきました。こうした背景から、アートコラージュは言語化の難しい感情を整理するきっかけとして広く活用されています。
さらに、作業そのものがクリエイティブで楽しいこと、完成すれば自作のアート作品にもなることから、趣味として楽しんでいる方も少なくありません。
アートコラージュのやり方
アートコラージュは、楽しんで実践しやすいセルフケア方法の一つです。
「コラージュを通して内観を行う」「コラージュには心理療法としての側面がある」と聞くと、意外に感じる方もいることでしょう。芸術や創作としてのコラージュではなく、内観のためにコラージュを取り入れる場合には、以下の手順を参考にしてみてください。
- 紙、写真や雑誌の切り抜き、シールといった素材を用意する
- 表現したい感情や感覚に合わせて、テーマを決める
- テーマに沿って、素材を自由にレイアウトしながら紙に貼っていく
作業中は、「なぜこの素材を選んだのか」「自分は今何を感じているのか」など、自分の心の動きに意識を向けながら取り組むのがポイントです。
完成したら、作品をじっくりと眺め、感じたことや考えたことを振り返ってみましょう。これまで意識していなかった自分自身の側面に気づくきっかけになるかもしれませんよ。
心の健康を保つ内観アイデア⑤瞑想
瞑想とは、呼吸や身体の感覚に意識を向けることで、思考を整理したり、感情を落ち着けたりする手法です。もともとは仏教の修行法として行われてきましたが、近年ではストレスケアやリラクゼーションの一つとして広く知られるようになりました。
「今、私は何を感じているの?」「私の本当の気持ちはどんなもの?」と自分に問いかけながら行うことで、自己理解を深めるきっかけになる可能性もあります。そのため、内観の手法として取り入れる方もいるようです。
さらに、最近では瞑想の効果について科学的な研究も進められています。例えば、マサチューセッツ大学のブリッタ・K・ホルツェル(Britta K. Hölzel)らによる研究では、8週間にわたり瞑想を行った参加者の脳において、記憶や感情に関わる部位に変化が見られたとも報告されています。
こうした知見から、瞑想が科学的な裏付けのあるストレスケアや内観の手法として注目されているのですね。
瞑想のやり方
瞑想は、今回ご紹介したセルフケアの中でも、特に人気の高い手法の一つです。
ですが、意外な注意点もあります。間違った方法で取り組んでしまうと、かえって心が不安定になったり、過去のトラウマを思い出してしまったりする危険性があるので、注意しましょう。
辛い思いをせずに瞑想を取り入れるためには、以下の手順を参考にしてみてください。
- あぐらをかいて座るか、横になる
- ゆったりと呼吸しながら、呼吸や身体の感覚に意識を向ける
- 思考や感情が浮かんできたら、感情的にならず、ただ静かに見守る
- 必要に応じて「今、私は何を感じている?」「この感情の理由は何だろう?」と優しく自分に問いかける
瞑想は、すぐに「やって良かった」と感じる方もいれば、コツをつかむまでに時間がかかる方もいます。また、始めたばかりの頃は、思うようにできなかったり、むしろ気持ちが不安定になったように感じたりすることもあるかもしれません。
そんなときは、瞑想をサポートしてくれるアプリを使うのも一つの手です。これまでにもご紹介してきたスマートフォンアプリ「Awarefy(アウェアファイ)」には、初心者でも取り組みやすいガイド付きの「瞑想音声」が複数収録されています。音声を聞きながら実践することで、コツをつかむきっかけになるかもしれませんよ。
内観したいならAwarefy (アウェアファイ)
「内観にもいろいろあるのは分かったけど、どれを選べばよいのか分からない」「やり方次第では危険性もあるって聞くと、サポートなしでやるのは不安……」そんな方におすすめなのが、スマートフォンアプリ「Awarefy(アウェアファイ)」です。
早稲田大学・熊野宏昭研究室との共同研究をもとに開発されたこのアプリには、認知行動療法やアクセプタンス&コミットメント・セラピーなど、実績ある心理療法の理論が応用されています。
さらに、心理学の知見とAI技術を融合させた設計も特徴の一つ。「AIタブ」機能を使うと、AIキャラクターのファイさんとチャットができ、フィードバックも返してくれます。
専門知識がなくても扱いやすいように設計されているので、「自分の心と向き合いたいけど、どうしたらよいのか分からない」という方にも取り入れやすいツールの一つです。
Awarefy(アウェアファイ)のおすすめ機能
アウェアファイには、内観に役立つ機能が多数搭載されています。
ここでは、その中から、内観を取り入れる際に特に活用されている3つの機能を厳選してご紹介。「内観を始めたいけど、何から始めたらよいか分からない」という方は、参考にしてみてくださいね。
コラム法+AIコメント
コラム法は、認知行動療法の理論に基づいて開発された記録機能です。
その日の出来事や感情、思考を整理したり、記録したりすることができます。また、AIコメント機能を利用すれば、記録した内容に対して、AIキャラクターのファイさんからコメントを受け取ることも可能です。
例えば、何でもネガティブに捉えてしまう方や、「白か黒か」といった極端な思考に陥りやすい方が、自分の考え方を見直すきっかけに取り入れているケースもあるようです。
客観的な視点を意識するためのサポート機能として、活用しやすいツールと言えるでしょう。
AIタブ
AIタブは、AIキャラクターのファイさんとチャット形式でやりとりができる機能です。
感情が高ぶったときや、記録したい出来事があったときに話しかけると、ファイさんがその内容を記録してくれます。
過去のチャットを振り返れば、自分の思考や感情の流れを見直すきっかけになるでしょう。また、記録をもとにジャーナリングやアートコラージュに活かすといった使い方をすることも可能です。
さらに、時間がないときの簡易的な記録手段としても役立つので、内観を無理なく続けたいと考えている方に役立つ機能の一つです。
コンディションの記録
コンディションの記録は、毎日朝と夜に感情や思考、体調を記録できる機能です。
朝は、心と体の状態をそれぞれ5段階評価で記録し、夜は心身の状態に加えて、その日の達成度と満足度も5段階評価で記録することができます。
継続して記録することができれば、自分の状態を客観的に捉える手助けになるでしょう。
さらに、記録したデータはグラフで確認できるため、心の傾向や体調の変化、調子を崩しやすいタイミングなどを視覚的に把握しやすくなります。
日々の心身の状態の変化を振り返ることで、自分に合った過ごし方を考えるヒントが得られるかもしれません。
まとめ
いかがでしたか。
内観には、さまざまな種類があります。とはいえ、全てを一度に試す必要はありません。大切なのは、「ちょっと気になる」「これならできそう」と思えるものを、一つだけ選んで始めてみること。
アナログでジャーナリングやアートコラージュを楽しんでもよいですし、紙もペンも用意せずに、瞑想で心を落ち着かせるのもおすすめです。
もっと気軽に取り組みたいときには、アウェアファイを活用するのも一つの方法です。隙間時間に取り入れやすいので、無理なく続けたいと考えている方にとっても使いやすいでしょう。
お申し込みはこちら→ストレスに負けないスキルが身につく【Awarefy】
心と向き合う時間を作ることは、自分を大切にするための第一歩です。ぜひ、あなたに合った方法で、少しずつ始めてみてくださいね。
- 参考文献
-
富山大学 学術研究部医学系神経性維新医学講座(n.d.) . 研究のご紹介. http://www.med.u-toyama.ac.jp/neuropsychiatry/research/research03.html
ハンズネットストア(2024) . 書く瞑想「ジャーナリング」とは?やり方や内容、効果を高める方法までご紹介. https://hands.net/hintmagazine/stationery/2312-journaling.html?srsltid=AfmBOoqGY9rHSMkzTMcaEQptcuJP934aEDp-M67-nXU-po75gRJMgai_
STUDY HACKER(スタディーハッカー) (2024). 10分で頭をリセット!「ブレインダンプ」の驚きの効果. https://studyhacker.net/braindump
コグラボ- Cognitive Behavioral Therapy Lab(2023). 認知再構成法とは?コラム表を用いた実践方法をわかりやすく具体例で解説. https://www.awarefy.com/coglabo/post/cognitive_reconstruction
日本コラージュ療法学会 The Japanese Association Collage Therapy(n.d.). コラージュ療法(collage therapy). https://www.kinjo-u.ac.jp/collage/instruction.html
Harvard Business Review(2015). マインドフルネスは脳を健全に保つ. https://dhbr.diamond.jp/articles/-/3331
漢方の知恵で、もっと健やかに美しく。Kampoful Life by クラシエの漢方(n.d.). 話題のマインドフルネス瞑想のやり方と効果!瞑想が人生の質を高める. https://www.kracie.co.jp/kampo/kampofullife/heart/?p=3142
Pennebaker, J. W. (1997). Writing about emotional experiences as a therapeutic process. Psychological Science, 8(3), 162–166. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1997.tb00403.x
Agarwal, P. K., Bain, P. M., & Chamberlain, R. W. (2021). The effects of brain dumps on student learning. Educational Psychology Review, 33, 293–310. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09528-1
Troy, A. S., Wilhelm, F. H., Shallcross, A. J., & Mauss, I. B. (2010). Seeing the silver lining: Cognitive reappraisal ability moderates the relationship between stress and depressive symptoms. Emotion, 10(6), 783–795. https://doi.org/10.1037/a0020262
Hölzel, B. K., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C., Yerramsetti, S. M., Gard, T., & Lazar, S. W. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, 191(1), 36–43. https://doi.org/10.1016/j.pscychresns.2010.08.006